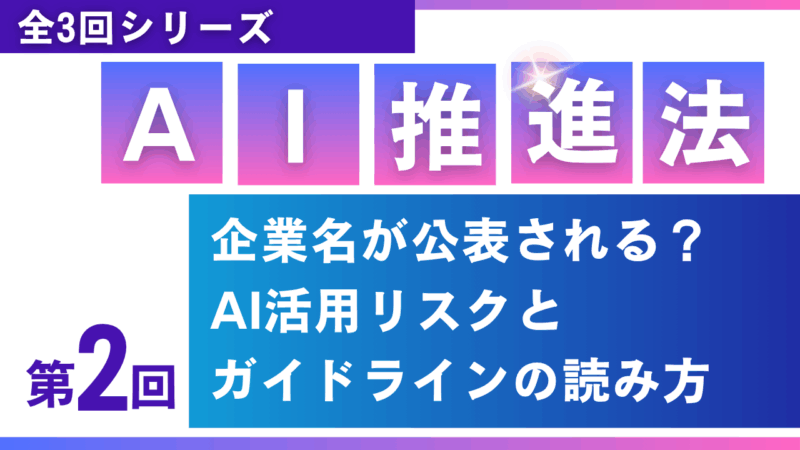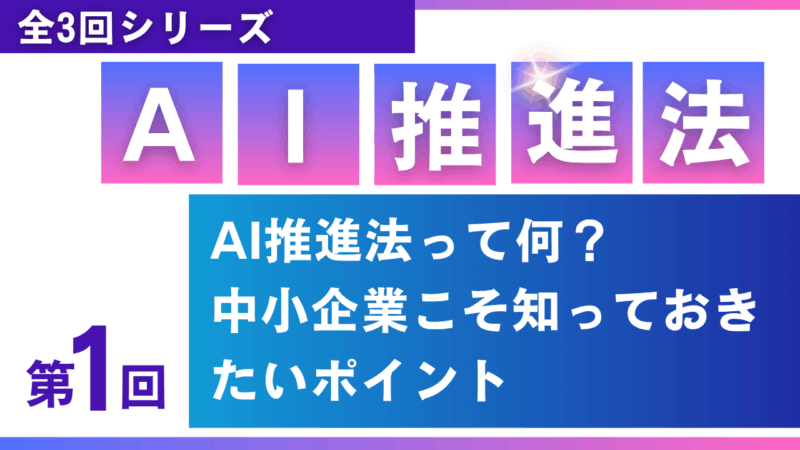第3回「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」
第3回「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」
このシリーズでは、2025年6月に施行された「AI推進法」について、中小企業の経営者・管理職が知っておくべきポイントを実務的に解説していきます。
- 第1回:AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント
- 第2回:企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方
- 第3回:AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応(本記事)
本記事では、第3回として「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」について詳しく解説します。
目次
はじめに
これまで2回にわたって、AI推進法の基本とリスク管理について学んできました。「理解はできたけど、実際にうちの会社では何から始めればいいの?」という方も多いでしょう。
AI推進法は「支援が中心」の法律だと分かっていても、「法律対応」と聞くと身構えてしまいがちです。しかし実際には、「当たり前のことを当たり前にやる」だけで十分対応でき、むしろ競争力向上のチャンスとして活用できます。
この記事では、中小企業が無理なく、確実に取り組める5つの実務対応を、具体的なツールやテンプレートとともにご紹介します。
1. 【実務対応①】社内ルールの整備|最低限のAI利用ガイドライン作成
①小規模企業向けシンプルルール
従業員10-20名程度の企業向け
A4用紙1枚で十分な基本ルール
【AI利用の基本ルール】
■ 基本方針
・業務効率化と品質向上のためAIを積極活用する
・ただし、リスクを理解し適切に利用する
■ 禁止事項(絶対にやってはいけないこと)
□ 顧客の個人情報をAIに入力する
□ 契約書や機密資料をAIに入力する
□ AI出力をそのまま顧客に提供する
□ 他社の著作物をAIで無断複製する
■ 推奨事項(積極的にやってほしいこと)
□ メール・資料の下書き作成に活用
□ アイデア出しやブレインストーミングに活用
□ AI出力は必ず人間が確認・編集
□ 問題があれば責任者に即報告
■ 責任者・相談窓口
・AI活用責任者:[責任者名]
・困ったときの相談先:[連絡先]つまり:完璧なルールを最初から作る必要はありません。「やってはいけないこと」を明確にして、相談窓口を設けるだけで十分です。
②中規模企業向け体系的ガイドライン
従業員30-100名程度の企業向け
より詳細な社内ガイドライン
【AI活用ガイドライン】
1. 目的・適用範囲
2. 基本原則
3. 利用可能な用途・禁止事項
4. セキュリティ要件
5. 責任体制・報告ルート
6. 教育・研修
7. 違反時の対応
8. 見直し・更新手順部署別の詳細ルール例
【営業部門】
・顧客情報は「A社様」「B社様」に匿名化
・提案書は必ず上司確認後に提出
・顧客との商談内容は入力禁止
【総務・経理部門】
・人事情報・給与情報は入力禁止
・契約書の作成は法務確認必須
・社内規程の改訂はコンプライアンス部門と協議
【技術・製造部門】
・技術仕様・製造ノウハウは入力禁止
・安全基準に関わる判断はAI任せにしない
・品質管理データは匿名化して活用③ルール策定のテンプレート
効率的なルール作成手順
Step1:現状把握(1-2時間)
- 現在使用しているAIツールの洗い出し
- 各部署での主な活用方法の確認
- 過去のトラブル・ヒヤリハット事例の整理
Step2:ルール案作成(2-3時間)
- 禁止事項リストの作成
- 推奨事項・活用例の整理
- 責任者・相談体制の決定
Step3:社内調整(1週間)
- 各部署からの意見聴取
- 実現可能性の確認
- 最終版の作成・承認
Step4:周知・教育(1ヶ月)
- 全社説明会の実施
- 部署別説明会の開催
- Q&A対応・個別相談
2. 【実務対応②】従業員教育|「やってはいけないこと」の周知徹底
①効果的な教育方法
企業規模別の教育アプローチ
小規模企業(10-30名)
- 朝礼・昼礼での5分間説明(月1回)
- メール・チャットでの注意喚起(週1回)
- 新規ツール導入時の個別説明
中規模企業(30-100名)
- 部署別研修会(四半期1回・1時間)
- eラーニング教材の活用
- 社内報・掲示板での情報発信
つまり:大がかりな研修は不要。日常業務の中で継続的に意識づけすることが重要です。
②教育内容のポイント
必ず伝えるべき3つのポイント
1. なぜAI活用ルールが必要なのか
「法律で決まったから」ではなく
「会社と顧客を守るため」「競争力向上のため」
という前向きな理由を説明2. 具体的な禁止事項と理由
❌ 「個人情報を入力してはいけません」
⭕ 「個人情報を入力すると、情報漏洩のリスクがあり、
会社の信頼失墜や損害賠償につながる可能性があります」3. 困ったときの相談方法
・誰に相談すればいいか
・どんなことを相談していいか
・緊急時の連絡方法③継続的な意識向上の仕組み
日常的な啓発活動
成功事例の共有
- 「AIでこんなに効率化できました」
- 「こんな使い方で品質が向上しました」
- 他社の先進事例の紹介
注意事例の共有
- 「こんなケースは注意が必要です」
- 他社のトラブル事例(匿名化)
- 業界団体からの注意喚起
定期的な振り返り
- 月次の利用状況確認
- 四半期の効果測定
- 年次のルール見直し
3. 【実務対応③】記録・管理体制|問題が起きたときに説明できる仕組み
①記録すべき情報の整理
最低限記録すべき項目
通常時の記録
【AI活用記録】
・使用日時・担当者
・使用したAIツール
・活用目的・内容
・出力結果の使用方法
・確認者・承認者重要案件の詳細記録
【詳細記録が必要な案件】
・顧客向け成果物での活用
・大量データの処理
・新規ツール・手法の導入
・外部との共同作業問題発生時の記録
【インシデント記録】
・発生日時・発見者
・問題の内容・影響範囲
・原因分析・調査結果
・対応措置・改善策
・再発防止策②管理体制の構築方法
現実的な管理体制
小規模企業の場合
【シンプルな体制】
・AI活用責任者:1名(経営者または管理職)
・記録担当者:各部署1名
・記録方法:Excelファイルまたはクラウドツール
・保存期間:3年間中規模企業の場合
【体系的な体制】
・AI推進委員会:委員長1名、各部署代表者
・事務局:総務・IT部門
・記録システム:専用ツールまたは既存システム活用
・監査体制:年1回の内部監査③トラブル対応フローの策定
問題発生時の対応手順
【緊急時対応フロー】
Step1:問題の発見・報告(即時)
↓
Step2:影響範囲の調査・確認(1-2時間)
↓
Step3:応急措置・被害拡大防止(即座)
↓
Step4:原因分析・詳細調査(1-3日)
↓
Step5:改善策の検討・実施(1週間)
↓
Step6:再発防止策の策定(2週間)
↓
Step7:社内共有・ルール更新(1ヶ月)外部対応が必要な場合
- 顧客への説明・謝罪
- 監督官庁への報告
- 専門家への相談
- メディア対応(必要に応じて)
4. 【実務対応④】情報収集体制|法改正やガイドライン更新への対応
①政府情報の効率的な収集方法
主要な情報源
政府関連
- 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局
- 経済産業省「AI政策」ページ
- 総務省「情報通信政策」ページ
- デジタル庁「AI関連政策」
効率的な情報収集方法
【推奨手順】
1. 各省庁のメルマガ・RSS配信に登録
2. 週1回の定期チェック(月曜朝など)
3. 重要情報は社内共有チャットで即座に連絡
4. 月1回の定期報告で全体像を整理②業界動向のモニタリング
民間情報源の活用
業界団体・商工会議所
- 業界固有のガイドライン
- 他社事例・ベストプラクティス
- セミナー・勉強会情報
専門メディア・調査会社
- IT・DX関連メディア
- 法務・コンプライアンス情報
- 海外動向・比較情報
つまり:政府情報だけでなく、業界の実践的な情報も収集することで、より現実的な対応策を検討できます。
③社内への情報共有の仕組み
効果的な情報共有方法
緊急度別の共有方法
【緊急(即時対応必要)】
・チャット・メールで全社即時配信
・責任者への電話・対面報告
・臨時会議の開催
【重要(1週間以内)】
・社内掲示板・イントラネット掲載
・部署責任者への個別連絡
・次回定例会議での報告
【参考情報(月次)】
・月次レポートに含めて配信
・社内勉強会での紹介
・ファイルサーバーでの情報蓄積5. 【実務対応⑤】支援制度の活用|国の支援を受けるための準備
①利用可能な支援制度一覧
AI推進法関連の支援制度
研究開発支援
【対象】
・AI技術の研究開発プロジェクト
・産学官連携の共同研究
・実証実験・パイロット事業
【支援内容】
・研究開発費の一部補助(2/3以内など)
・専門家派遣・技術指導
・実証フィールドの提供人材育成支援
【対象】
・従業員向けAI研修
・専門人材の採用・育成
・リスキリング・職業訓練
【支援内容】
・研修費用の補助(1/2以内など)
・専門人材の紹介・派遣
・オンライン教材の無料提供設備投資支援
【対象】
・AIツール・システムの導入
・クラウド環境の構築
・セキュリティ対策の強化
【支援内容】
・導入費用の補助(1/3以内など)
・税制優遇措置
・低利融資制度②申請・活用のポイント
支援制度活用の成功法則
事前準備
【必要な準備】
・AI活用計画の明文化
・予算・スケジュールの具体化
・効果測定指標の設定
・社内体制の整備証明申請時のポイント
【申請書作成のコツ】
・具体的な数値目標を設定
・地域経済・雇用への効果をアピール
・他社との差別化ポイントを明確に
・継続的な取り組み姿勢を示す採択後の注意点
【実施中の留意事項】
・定期的な進捗報告
・計画変更時の事前相談
・成果の適切な記録・保存
・知的財産権の適切な管理③成果を最大化する方法
支援制度の戦略的活用
他の施策との連携
- DX推進補助金との組み合わせ
- IT導入補助金との併用
- 地方自治体の独自支援制度の活用
長期的な視点での活用
- 段階的な支援制度の活用計画
- 成果を次の支援申請に活用
- ネットワーク構築・情報交換の機会として活用
つまり:支援制度は「単発の資金調達」ではなく「継続的な競争力向上の仕組み」として活用することが重要です。
まとめ
AI推進法への対応は、「法律だから仕方なく」ではなく「会社の競争力向上のチャンス」として取り組むことで、大きな成果を得られます。
5つの実務対応まとめ
- 社内ルール整備:A4一枚の簡単なルールから始める
- 従業員教育:日常業務の中で継続的に意識づけ
- 記録・管理体制:最低限の記録で説明責任を果たす
- 情報収集体制:週1回のチェックで最新動向を把握
- 支援制度活用:戦略的に活用して競争力向上を図る
シリーズ全体の振り返り
- 第1回:AI推進法は支援中心の法律(チャンスと捉える)
- 第2回:常識的な範囲なら企業名公表のリスクは低い
- 第3回:適切な対応で競争力向上につなげられる
成功のポイント
- 完璧を目指さない:できることから段階的に実施
- 継続的改善:問題があれば都度見直し・改善
- 前向き活用:リスク管理と競争力向上の両立
- 外部連携:政府支援制度や専門家を積極活用
AI推進法は「規制」ではなく「企業の成長を支援する仕組み」です。適切に対応することで、政府支援を受けながら競争力を向上させ、同業他社との差別化を図ることができます。
まずは今日から、できることを一つずつ始めてみませんか?
このシリーズで学んだ知識を活用して、AI推進法を味方につけましょう。
第一歩:社内のAI利用状況を整理(30分)
第二歩:簡単な社内ルールを作成(1時間)
第三歩:政府支援制度の情報収集(週1回)
シリーズ記事一覧
- 第1回「AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント」
- 第2回「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」
- 第3回「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」(本記事)
関連記事
- 生成AI入門シリーズ(全5回)はこちら