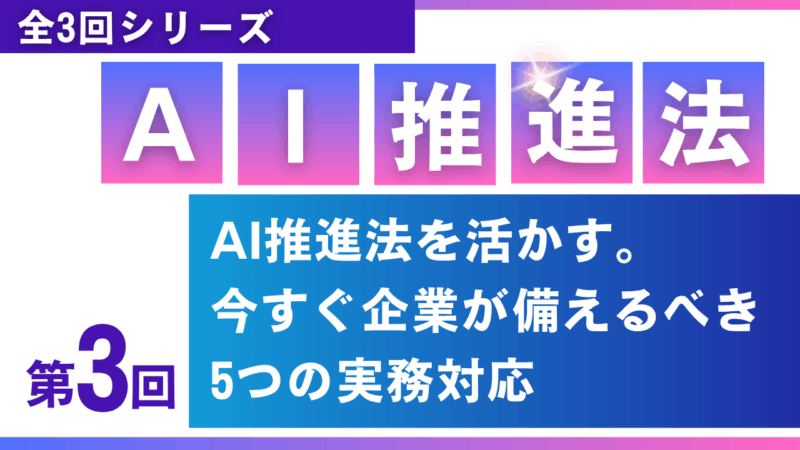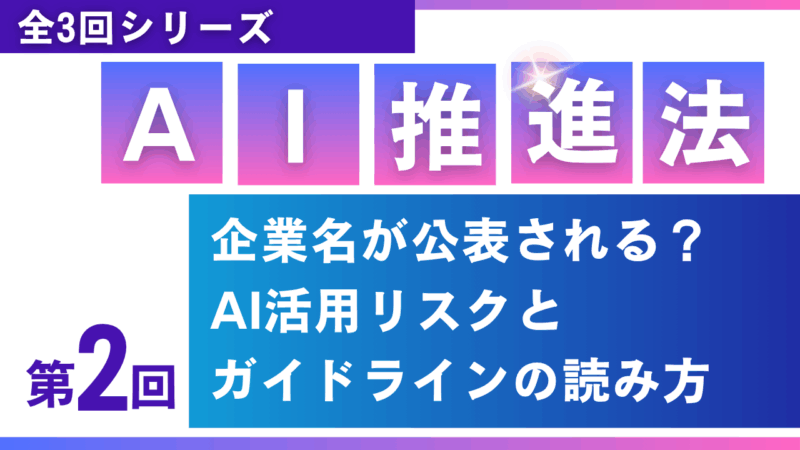第1回「AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント」
全3回シリーズ「AI推進法を理解する|中小企業のための実務ガイド」|第1回「AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント」
このシリーズでは、2025年6月に施行された「AI推進法」について、中小企業の経営者・管理職が知っておくべきポイントを実務的に解説していきます。
- 第1回:AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント(本記事)
- 第2回:企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方
- 第3回:AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応
本記事では、第1回として「AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント」について詳しく解説します。
目次
はじめに
「AI推進法って聞いたことはあるけど、結局何の法律?」「うちの会社にも関係あるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。
2025年6月に施行されたAI推進法は、日本で初めてのAI分野の包括的な法律です。「法律」と聞くと「また新しい規制?」と身構えてしまいがちですが、実は「AI活用を後押しする法律」という側面が強いのが特徴です。
この記事では、「法律は難しそう」と感じている経営者・管理職の方にも分かりやすく、AI推進法の基本と中小企業への影響をお伝えします。
1. AI推進法ができた背景:なぜ今、この法律が必要だったのか
①生成AIブームと企業の困惑
2022年末のChatGPT登場以降、生成AIが急速に普及しました。
多くの企業が「使ってみたい」と興味を示す一方で、「どう使えばいいのか分からない」「リスクが心配」という声も高まりました。
企業が直面した課題
- セキュリティや著作権のリスクが不明確
- 社内でどんなルールを作ればいいか分からない
- 競合他社に遅れたくないが、失敗も怖い
- 政府の方針や支援策が見えない
②日本のAI競争力の遅れ
データで見る日本の現状
AI分野への民間投資額(2023年)
- 1位:米国 約672億ドル
- 2位:中国 約78億ドル
- 12位:日本 約7億ドル
生成AI利用経験者の割合
- 米国:46%
- 中国:56%
- 日本:9%つまり:日本は技術も活用も世界から大きく遅れており、このままでは国際競争で取り残される危機感がありました。
③国民の不安の高まり
生成AI普及と同時に不安も拡大
- ディープフェイクによる偽情報の拡散
- 個人情報漏洩のリスク
- 著作権侵害の問題
- 雇用への影響
調査結果:「AIには何らかの規制が必要」と感じる日本人は約77%
政府は「このままでは日本だけが取り残される」という危機感と、「国民の不安に応える必要がある」という両方の課題に直面していました。
2. AI推進法とは?基本的な仕組みを理解する
①正式名称と施行日
正式名称:「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」 通称:AI推進法 施行日:2025年6月4日
②「推進法」の意味:規制ではなく支援が中心
AI推進法の基本的な性格
❌ 「規制法」ではない
- 特定のAI技術を禁止する条項はない
- 違反に対する罰則もない
- 厳格な事前審査や許可制もない
⭕ 「支援法」が中心
- 研究開発への投資拡大
- 人材育成プログラムの充実
- 企業への技術支援
- 規制緩和・実証実験の推進
つまり:「AIを規制する法律」ではなく、「AIの発展を国として支援する法律」です。
③AI戦略本部とAI基本計画
新設される推進体制
AI戦略本部
- 本部長:内閣総理大臣
- 構成員:全閣僚
- 役割:政府横断のAI戦略統括
AI基本計画
- 今後5年程度の具体的な目標・施策
- 研究開発、人材育成、産業振興の方針
- 年1回見直し・更新
つまり:政府が本気でAI分野に取り組む体制を法律で明文化しました。
3. 他国との違い:日本独自のアプローチとは
①EU:厳格な規制で安全性重視
EUのAI法(AI Act)の特徴
- 一部のAI技術を明示的に禁止
- 高リスクAIには事前認証や詳細な遵守義務
- 違反時の制裁金は最大で数千万ユーロ
狙い:人権・消費者保護を最優先
②米国:市場主導で自主規制中心
米国のアプローチ
- 包括的なAI法は制定せず
- 業界の自主規制を重視
- 大統領令による行政措置で補完
狙い:市場の創意工夫を最大限活用
③日本:イノベーション促進とリスク管理の両立
日本のユニークな特徴
項目EU米国日本基本姿勢規制重視自主規制促進+最低限の規律罰則巨額制裁金なしなし政府関与強い限定的中程度企業負担重い軽い軽め
つまり:日本は「厳しすぎず、緩すぎず」の中間路線で、企業がAIを活用しやすい環境作りを目指しています。
4. 中小企業にとって追い風?負担?影響を整理
①期待できる支援制度
研究開発支援の拡充
- AIツール導入への補助金
- 実証実験の規制緩和
- 大学・研究機関との連携支援
人材育成支援
- 従業員向けAI研修への助成
- リスキリング(職業訓練)プログラム
- 専門人材の派遣・紹介
実例:すでに始まっている支援
- 中小企業向けDX推進補助金の拡充
- AI活用事例集の公開
- 業界別ガイドラインの策定②新たに発生する責務
企業に求められる協力
- 政府のガイドラインへの協力
- 問題発生時の情報提供
- AI活用状況の報告(必要に応じて)
重要:現時点では「努力義務」レベル
- 罰則はない
- 強制力も限定的
- まずは自主的な取り組みが中心
③「様子見」のリスク
早期対応のメリット
- 政府支援制度を優先的に活用
- 業界ガイドライン策定への参画
- 競合他社との差別化
様子見のデメリット
- 支援制度の定員に間に合わない
- 後から規制が厳しくなる可能性
- 競合に技術力で差をつけられる
つまり:中小企業にとって、AI推進法は「負担よりもチャンスの方が大きい」法律と言えます。
まとめ
AI推進法は「AIを規制する法律」ではなく「AIの活用を国として支援する法律」です。
押さえておくべき5つのポイント
- 背景:日本のAI競争力向上と国民の不安解消が目的
- 性格:規制よりも支援が中心、罰則なし
- 体制:AI戦略本部とAI基本計画で政府が本格推進
- 特徴:EU・米国とは異なる「中間路線」アプローチ
- 影響:中小企業には支援の機会が拡大、新たな負担は軽微
中小企業にとっての戦略
- チャンス重視:政府支援制度の積極活用
- リスク管理:最低限のルール整備で備える
- 早期対応:競合との差別化機会として活用
次回は「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」について詳しく解説します。
シリーズ記事一覧
- 第1回「AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント」(本記事)
- 第2回「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」
- 第3回「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」
関連記事
- 生成AI入門シリーズ(全5回)はこちら