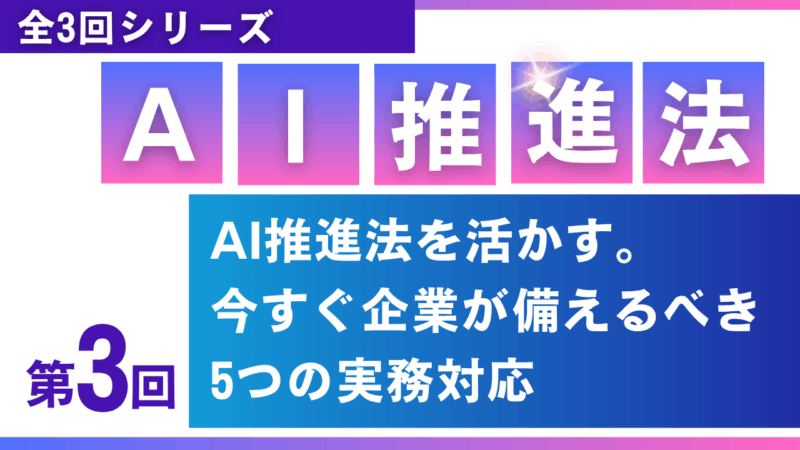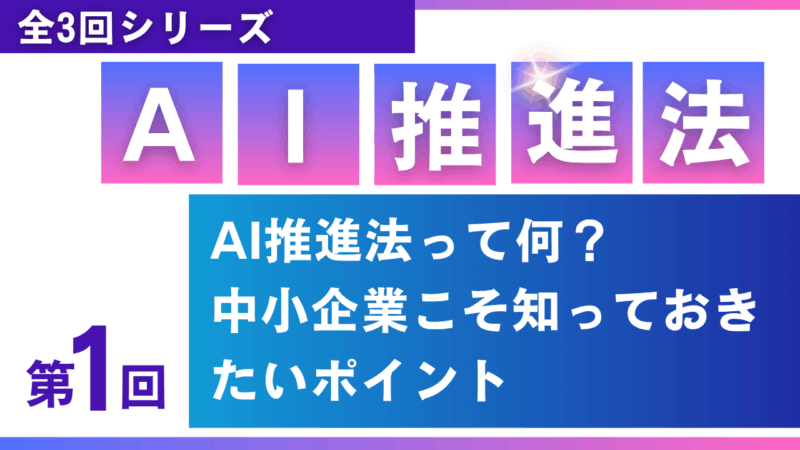第2回「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」
第2回「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」
このシリーズでは、2025年6月に施行された「AI推進法」について、中小企業の経営者・管理職が知っておくべきポイントを実務的に解説していきます。
- 第1回:AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント
- 第2回:企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方(本記事)
- 第3回:AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応
本記事では、第2回として「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」について詳しく解説します。
目次
はじめに
前回、AI推進法は「支援が中心で罰則もない」とお伝えしましたが、「じゃあ何をやっても大丈夫?」というわけではありません。
「企業名が公表される可能性がある」と聞いて、「うちは大丈夫?」「何をしたら問題になるの?」と不安に感じている方も多いでしょう。
この記事では、具体的にどんな場合に問題となり、どう対応すればリスクを避けられるのかを、「怖がりすぎず、でも甘く見すぎず」のバランスで解説します。
1. 「企業名公表」の仕組み:いつ、どんな場合に発動される?
①政府の「調査権限」とは何か
AI推進法で新たに創設された権限
前回お伝えした通り、AI推進法には罰則がありません。しかし、政府には新たな「監督権限」が付与されました。
政府ができること
- 情報収集・調査:AI開発・活用の動向把握
- 事案分析:問題のあるAI活用事例の調査
- 指導・助言:企業への改善要請
- 情報提供:国民・企業への注意喚起
- 必要措置:状況に応じた対応(企業名公表を含む)
つまり:「取り締まり」ではなく、「指導・改善」が目的の権限です。
②企業名公表までの流れ
段階的な対応プロセス
【第1段階】情報収集・確認
↓
【第2段階】非公式の指導・助言
↓
【第3段階】正式な改善要請
↓
【第4段階】企業名公表(最終手段)重要:いきなり公表されることはありません
- まずは改善の機会が提供される
- 企業側の説明・弁明の機会も確保
- 悪質性や影響度を総合的に判断
③公表される条件と基準
公表が検討される可能性がある場合
重大性の基準
- 多数の国民に影響を与える問題
- 社会的な混乱や不安を引き起こす事案
- 他企業への悪影響が懸念される事例
悪質性の基準
- 政府の指導・助言を繰り返し無視
- 意図的・計画的な法令違反や社会的害悪
- 改善意欲が見られない、隠蔽しようとする姿勢
つまり:うっかりミスや初回の問題で即座に公表されることはなく、悪質で改善意欲のない企業が対象となります。
2. どんな場合が「問題」になる?具体的な違反例を知る
①個人情報・機密情報の不適切な処理
よくある問題例
顧客情報の流出
❌ 問題となる例:
- 顧客の個人情報をAIの学習データに無断使用
- 生成AIに機密情報を入力して外部漏洩
- 適切な同意なしに個人データを分析
⭕ 適切な対応:
- 個人情報は匿名化してから活用
- 機密情報はAIに入力しない
- 利用目的を明確にして同意を取得社内情報管理の不備
❌ 問題となる例:
- 社員が無断でChatGPTに契約情報を入力
- AIツールのセキュリティ設定が不適切
- データの保存・削除ルールが未整備
⭕ 適切な対応:
- 社内利用ルールの明文化
- セキュリティ設定の定期確認
- データ管理手順の策定②著作権侵害や知的財産権の問題
注意が必要な事例
生成AIの出力利用
❌ 問題となる例:
- AI生成コンテンツをそのまま商用利用
- 他社の著作物に類似した内容を無断使用
- AIに他社の機密情報を学習させる
⭕ 適切な対応:
- AI出力は必ず人間が確認・編集
- 類似性チェックツールの活用
- 学習データの出所を適切に管理③ディープフェイクなど悪用事例
重大な問題となる可能性
悪用の典型例
- 政治家や有名人の偽動画作成
- 競合他社を貶める偽情報の生成
- 詐欺や犯罪に利用される偽コンテンツ
つまり:明らかに悪意のある利用や、社会に重大な害をもたらす使い方は厳しく対処される可能性があります。
3. AI倫理ガイドラインの実務的な読み方
①「適正な活用」の具体的な意味
政府が求める「適正な活用」とは
基本原則
- 人間中心:最終判断は人間が行う
- 透明性:AIの仕組みや判断根拠を説明できる
- 公正性:差別や偏見を生まないよう配慮
- 安全性:予期しない害を防ぐ対策を講じる
- 責任:問題発生時の対応体制を整備
実務での解釈例
【人間中心の原則】
- 重要な契約判断はAI任せにしない
- AI出力は必ず人間が最終確認
【透明性の原則】
- 「AIが作成しました」と明記する
- 顧客にAI利用を適切に説明
【公正性の原則】
- 採用判断でAIを使う場合は偏見チェック
- 特定の属性を不当に排除しない
【安全性の原則】
- 誤情報の拡散を防ぐ仕組み作り
- 定期的な動作確認・品質チェック②透明性・説明可能性への対応
実際に求められること
顧客・取引先への説明
- AIを活用したサービスであることの開示
- AIの判断根拠の概要説明
- 人間による確認・監督体制の説明
社内での透明性確保
- AI活用の目的・範囲の明文化
- 責任者・担当者の明確化
- 問題発生時の対応手順の策定
③データ管理と品質確保
データ品質管理のポイント
入力データの管理
- データの出所・信頼性の確認
- 個人情報・機密情報の除外
- 定期的なデータ更新・メンテナンス
出力結果の品質確保
- 明らかな誤りのチェック体制
- 偏見や差別的内容の確認
- 法的問題がないかの確認
4. 「調査が来る」ときの対応方法
①情報提供要請への対応
想定される要請内容
基本的な情報
- AI活用の目的・範囲
- 使用しているAIツール・サービス
- データの取得・処理方法
- 安全性確保の取り組み
問題発生時の詳細情報
- 問題の発生経緯・原因
- 影響範囲・被害状況
- 改善・対策の実施状況
対応のポイント
- 正直かつ正確な情報提供
- 隠蔽は絶対に避ける
- 改善意欲を明確に示す
- 専門家への相談も検討
②社内体制の整備ポイント
調査対応の準備
担当者の明確化
- AI活用の責任者を決める
- 外部対応の窓口を一本化
- 法務・コンプライアンス担当者との連携
情報の整理・管理
- AI活用状況の一覧作成
- 利用ルール・手順の文書化
- 問題発生時の対応フローの策定
③記録・証拠の管理方法
保存すべき記録
通常時の記録
- AI活用の目的・経緯
- 使用したデータの出所・内容
- 安全対策の実施状況
- 従業員への教育・研修記録
問題発生時の記録
- 問題の発見・報告経緯
- 原因調査・分析結果
- 対策・改善の実施内容
- 再発防止策の検討過程
5. 中小企業でも最低限押さえるべきポイント
①「やってはいけないこと」チェックリスト
絶対に避けるべき行為
□ 個人情報をAIに無断で学習させる
□ 他社の著作物をAIで無断複製・改変する
□ ディープフェイクで虚偽情報を作成・拡散する
□ AIの判断だけで重要な意思決定を行う
□ 問題発生時に隠蔽・虚偽報告をする
□ 政府の指導・助言を無視し続ける
□ 差別的・偏見的なAI出力を放置する
□ セキュリティ対策を怠り情報漏洩を起こすつまり:常識的に考えて「これはまずい」と思うことをAIでやらなければ、大きな問題になることはありません。
②小規模企業向けの現実的な対応策
最低限の対応(従業員10-30名程度)
ルール策定
- A4用紙1枚程度の簡単な利用ルール
- 「やってはいけないこと」の明文化
- 責任者・相談窓口の明確化
教育・周知
- 年1-2回の簡単な説明会
- 新規ツール導入時の注意事項共有
- 問題発生時の報告ルートの周知
記録・管理
- 使用しているAIツール一覧
- 重要な利用事例の記録
- 問題・トラブル発生時の対応記録
③外部サポートの活用方法
専門家への相談タイミング
事前相談が推奨される場合
- 大量の個人データをAI分析に活用
- AI生成コンテンツの商用利用
- 顧客向けAIサービスの提供開始
問題発生時の緊急相談
- 情報漏洩・セキュリティ事故
- 著作権侵害の疑い
- 政府からの調査・要請
相談先の例
- IT・知財専門の法律事務所
- AI活用コンサルティング会社
- 業界団体・商工会議所
- 中小企業向けDX支援機関
まとめ
AI推進法の「企業名公表」は、悪質で改善意欲のない企業を対象とした最終手段です。常識的な範囲でAIを活用し、問題があれば誠実に対応する企業であれば過度に心配する必要はありません。
リスク回避の5つのポイント
- 基本ルール:個人情報・機密情報の取扱いに注意
- 透明性確保:AI利用を適切に開示・説明
- 品質管理:AI出力は必ず人間が最終確認
- 記録保持:活用状況と安全対策の記録
- 誠実対応:問題発生時は隠蔽せず改善に取り組む
中小企業の実務対応
- 完璧を目指さない:最低限のルールから始める
- 段階的改善:問題を発見したら都度改善
- 外部活用:不安な場合は専門家に相談
- 前向き姿勢:リスク管理と活用推進の両立
重要:過度に萎縮する必要はありません 政府の狙いは「AI活用の促進」であり、企業を委縮させることではありません。適切なルールの下で積極的にAIを活用することが、競争力向上につながります。
次回は最終回として「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」について詳しく解説します。
シリーズ記事一覧
- 第1回「AI推進法って何?中小企業こそ知っておきたいポイント」
- 第2回「企業名が公表される?AI活用リスクとガイドラインの読み方」(本記事)
- 第3回「AI推進法を活かす。今すぐ企業が備えるべき5つの実務対応」
関連記事
- 生成AI入門シリーズ(全5回)はこちら